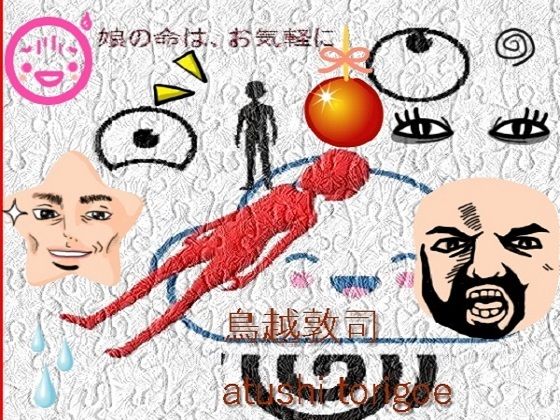凌辱を救え 派面ライダー
ビルの谷間でセーラー服を着たピチピチの若い娘が、目の前に立っている、痴漢風の若者を嫌悪の眼で見ると、
「助けて!派面ライダー!」
と叫んだ。彼女は右手に握り締めた、小さなリモコンのようなものをスカートのポケットの中に戻す。セーラー服の上着の胸は、未成年者とは思えない程、豊かな曲線を描いている。彼女の前の痴漢らしい男は、大声を上げられて驚いたが、誰も来ないので、彼女に数歩近づき、胸に触ろうと右手をあげた瞬間、
「とおおおおっ!」
という男の掛け声が聞こえて、痴漢らしき若者は右手を蹴られていた。
「うわっ。」
痴漢のような青年は声をあげた。彼の眼には、白のアイマスクのようなものを目の辺りにつけた中年の男性、服装は白バイの警官に似たものだが、白バイの警官の服装の白い部分が赤色になっている、その男が連続的に右足を上げたのが見えた瞬間、頭の、こめかみを蹴られてドウ、とアスファルトの地面に痴漢未遂の、その男は倒れた。
顔は、どう見ても二十歳のセーラー服の女は、そこそこの、いい女だ。彼女は両手を胸の前に握り締めて、祈りのようなポーズを取ると、
「ありがとう、派面ライダー。」
と感謝の言葉を口にした。
白バイの警官に似た、その中年男は、
「いえ、どういたしまして。ここらを通りかかっていた、ものですからね。今日は水曜日で、ぼくの休みの日ですよ。リモコンの無線で呼ばれたのに、気づきました。」
と照れながら、自分の行動を説明した。ビルの谷間で、人は通るのが少なく、道の先は行き止まりで、ビルの壁だ。大人二人が横に並べば、谷間の道は塞がる。人の通っている道からは、そこは五メートルは離れている。派面ライダーと呼ばれた男のバイクは、ビルの谷間の入り口近くに停めてあった。
「派面ライダー、お礼に抱いてください。」
セーラー服の二十歳の女は、ビルの壁を背に、声を、中年の背は中背で、白いアイマスクの男にかけた。
「ええっ?いいのかなー、そんな事して。」
「ここなら、人も気づきません。あんな、勃起もしない若い奴に触られるより、中年の、あなたの方が好き。」
百五十六センチの彼女は、大きな胸を自分で両手で掴むと、
あはん、と悶えた。それを見るなり、派面ライダーは白バイの警官の服装に似た格好で、女子校生に近寄ると、
「ごっつあん、しようかな。いただきますよ、あなたを。」
と言うと、彼女を抱きしめた。大きな胸が派面ライダーの腹の上あたりで潰れる。派面ライダーの右手は、女子校生のスカートの尻を撫で擦った。尻を触られて彼女は、喘ぎ始める。
派面ライダーは、そこで顔を下に向けていって、彼女にキスをした。彼女は派面ライダーの中年の唇が触れると、唇を開いて舌を出し、派面ライダーの唇を舐める。中年男の派面ライダーも唇を開き、女子校生の唇の中の赤い舌に、自分の舌を絡めた。
派面ライダーは女子校生のスカートの前を擦ると、彼女の股の間は、スカートの上から触っても濡れていた。女子校生は唇を離すと、
「派面ライダー、早く入れてよ。」
と、おねだりした。
「ああ、わかったよ。」
すでに勃起していた彼の股間のモノは、ズボンの膨らんだところが女子校生の臍の下あたりに当たっていたのだ。
派面ライダーは女子校生のスカートの中に手を突っ込むと、ショーツを下げて彼女の膝の辺りまで下ろした。それから自分のズボンのジッパーを降ろすと、容易に大きなキノコのようなモノは、パンツの切れ目から突き出てくる。
派面ライダーは膝を屈めて、少し上げると、彼女の濡れた裂け目にスルリと淫欲棒を入れた。女子校生は、
「はああああーっん。こんな、ところで、するのは、初めて。」
と悶え始める。彼女のピンクの内部は、ざらついていて、自分の淫欲棒が刺激されて気持ちいい。太陽は南中していた。真上から照りつける太陽の光は、女子校生の淫欲裂から、派面ライダーの淫欲棒が出ては、入るのを照らしつけている。そのうち中年の派面ライダーは、膝が痛くなってきた。ので、淫欲棒を一旦抜いて、
「バックからしようよ。膝が痛くてね。」
と女子校生に話す。
「いいよ。後ろから突いてくれた方が、もっと気持ち、いいかも。」
女子校生はクルリと向きを変えると、ビルの壁に両手を突いて、大きな尻を突き出すと、スカートを右手で上げた。
すいか、のような彼女の尻肉の下の中央には、もっこり、と、ふくらんだ肉の中心に淫欲の裂け目が派面ライダーの眼についた。彼は、まだ天を向いている自分の欲棒のかたまりをズーン、とスムーズにズームインさせたのだ。
「ああん、大きいのを感じるわ、派面ライダー。」
女子校生は、黄色い声を上げる。派面ライダーは、赤い手袋をしたまま彼女の尻を抱えて思う存分、突きまくった。ずんずん、ずいっずいっ、と。「ああん、もう、こわれて、しまいそうだわっ、いい、天国に、いきそうっ。」
十分もすると、女子校生の内部の締め付けが強まってきて、派面ライダーは、
「ああ、おっ。」
と声を上げると、どくっ、どくっと女子校生の淫穴の中に、出しきれるものは全て出した。
波山飛苧(なみやま・とぶお)四十歳は、うだつの、あがらないサラリーマンだった。福岡市内の不動産会社に勤めているが、不動産会社を転々としていた。主に賃貸住宅の仲介をしている不動産屋を流れ歩いている彼は、いつでもヒラの社員だ。
福岡県福岡市は人口百五十万人を越えて、マンションやビルも増える一方、不動産会社も増えているので競争は厳しい。
東京からの不動産会社も参入してくる。福岡市の都心部は東京さながらの人口密集地帯で、いつの日か二百万を超える人口になるに違いない。
波山飛苧の父は福岡県庁に勤めとおした役人で、長男の飛苧に波の山を越えて飛ぶ、飛び魚のような人間になってほしい、という思いから飛苧と名づけたのだ。
高校を出た飛苧はバイク便のライダーとなって、重要書類を届けて回っていたが、働きながら学べる不動産の専門学校に通い、宅地建物取引主任者の資格を取り、不動産会社に転職した。
しかしながら、不動産物件の案内などは自動車で回るのが常だ。飛苧は自動車運転免許も持っているので、顧客の案内も会社の車で行っていたが、好きなバイクに乗れないので、不満が、つのっていた。
飛苧は三十にして、ワンルームの中古分譲マンションを買い、そこで暮らしている。福岡市の中心に近いワンルームマンションだ。三十五歳の時に変装趣味を覚えて、白バイ警官の服装を購入した。白い部分を赤く染めると、250ccのバイクに乗り、サングラスを掛けて車道を走った。
道行く車の運転手や、バイクの運転者は彼を白バイの警官と間違えた。よく見ると、赤い色の部分がある服装なので、気がつくはずだが、気がつかない。飛苧は爽快になった。
彼はマンションの七階にある自分の部屋に戻ると、アイマスクに似た、目の部分は穴の開いたものを、両目に当てて、後頭部にゴムひもを掛けると、
「変チン、」
と声を出しながら、両腕を、まっすぐにして肩の上に上げた。万歳の格好に似ているが、両手のひらは前にではなく、横を向いている。互いの手の平が、向き合っている形だ。
「おおっ。」
と飛苧は次に声を出すと、両手を降ろして、股間に持っていく。両手でズボンの上から自分のモノを触ると、すでに、それは固く太くなっていた。
(いける、じゃないか。これで、変チンすれば即、勃起している。どんな女とも、すぐに、やれるだろう。とは、いっても、若い女となら、だが。)
飛苧は高級物件を案内したキャバクラの女性と、その部屋に行った時に、二十三歳の、その可愛い女は、
「誰も居ないしさ。ここでセックスしようよ。」
と玄関のドアを飛苧が閉めた時に誘った。
「え、まさか、そんなこと、できるわけ、ないでしょう。」
飛苧は一応、否定した。キャバクラの可愛い女は、ふん、と笑って、
「勇気ないのねー。わたし、お客さんから毎晩誘われているけど、五人に一人としかセックスしないのよ。今は二月で客が少ないから、マンコに入れる本数が減ってるからさ、あんたのモノ入れてくれたら、ここの部屋に決めるよ。」
と話して、スカートを自分の胸まで引き上げた。
彼女の股間は、真っ赤なショーツだった。まるで、闘牛が闘牛士の赤い布キレに誘われるように、飛苧は興奮して勃起した。
「お客さん、いいんですね。会社には内緒ですよ。」
と灰色のズボンの前を膨らませて、飛苧は聞いた。
「そんな事、誰にも言わないわよ。立っているじゃない。ちんこ出したら?」
とキャバ嬢は挑発した。
「出しますよ。そーれ。それから、こうする。立ちシックスナイン。」
飛苧は瞬時に自分の肉棒をジッパーから引っ張り出すと、キャバ嬢の前で逆立ちをして、手を交互に動かして逆立ちのまま、身を反転させた。
立っているキャバ嬢の目の前に、飛苧の勃起肉棒が床を向いて硬直していた。
「ええー、凄いわ。しゃぶるね、ちん棒。」
細い白い指で、キャバ嬢は飛苧の血管の浮き出たモノを握って、亀頭から口に入れると、
ふぐ、ふぐ、と音をたてながら、自分の頭を長い髪を振って上下に揺らせた。飛苧の目の前に、キャバ嬢の股間は、なかった。
「泉沢さん、あなたのオマンコは見えませーん。」
と逆立ちして、太くさせた肉棒をしゃぶられながら飛苧は、わめいた。キャバ嬢は口から太い肉棒を抜くと、
「ごめん。しゃがむわね。ショーツは、わたしが、おろすよ。」
彼女は、しゃがんでショーツを膝まで降ろすと、そのまま、自分の割れ目が飛苧の顔の前に見えるように近づけた。ああ、かわいいキャバ嬢の、男の棒を咥えたくて、しょうがない膨らみと、少し開いたピンクの縦の裂け目が飛苧の眼に、うつったのだ、彼は逆立ちの手を交互に少し進めると、キャバ嬢、泉沢のマンコの縦の淫裂に口をつけて、舌を出して舐め捲くると、
「ああー、いいわー。逆立ちしている男に、アソコを舐められるのは初めてよ。」
と悶えて自分の乳房を両手で持って、飛苧の床に向いて硬直している肉を乳房に、はさんだ。上着の上からではあるが、気持ちいい、と飛苧は感じると
ピュッ、ピュッ
泉沢の上着の胸に射精してしまった。彼女は慌てて、
「ちょっとー、何するのよー、この上着、高いんだから。カシミヤなのよ、五万するの。」
文句を言う。萎えたチンコは、やはり逆立ちしているので、床を向いている。その姿勢で飛苧は、
「すみません。ここの家賃七万円でしたね。手数料は一か月分なので、五万円ぼくが払いますから。」
と話す。キャバ嬢は、にこり、として、
「そうしてね。わたしの福岡銀行の口座に、入れといてよ。もし振り込まなかったら、この件は、あんたの会社に、ばらすわよ。」
「わかりました。なるべく早急に・・・。」
「いつまで逆立ちして、小さなチンコを、ぶらさげてるのよ。」
「すみません。戻ります。」
飛苧は手を動かすと、背中を泉沢に向けて、足は彼女の目の先の床面に下ろした。着地して、慌てて小さくなったモノをズボンに仕舞い込んだ。
と、いうような過去もあった。紹介した部屋で、水商売や風俗の女は誘ってくる場合もあったが、思うように挿入した事はない。それは追々、彼の追想で出てくるかと思う。
さて、彼の変チンポーズだが、飛苧は変チンと叫んで、両腕を真っ直ぐに天に上げた時に、頭の中でAV女優の裸体を思い浮かべる事にしている。旬の女優が、いい。数年前に人気があったAV女優も、いつのまにか消えてしまうことが多いものだ。
「変チン、」
で、AV女優の裸の股間に、頭の中の視線を合わせると、むずむず、と肉棒に血液が流れ込み、
「おおっ。」
で完全に勃起している。
最初に暴漢に追い詰められた女性は、キャバ嬢だ。彼女は中洲のキャバクラ、「女子校生」に勤めている。波山飛苧も時々、遊びに行くキャバクラである。彼は、
「おれ、変身ポーズでチンコ立てられるんだ。」
と接待している女子高のセーラー服を着た、二十歳のキャバ嬢に話した。
「きゃっ、チンコなんて露骨だわ。でも、すごいのね。」
と持ち上げてくる。
「ここで、して見せようか。」
「いいわ、やってよ。」
飛苧は立ち上がると、
「変チン、」
と叫び、両手を手のひらを内側に向けて、真っ直ぐに挙げた。その時、彼の頭の中にはAV女優の裸が浮かんでいる。
「おおっ。」
と叫んで、股間に手を回すと、完全に勃起しているのが、目の前にいるキャバ嬢にも分かった。その二十歳のキャバ嬢は手を叩いて、
「すごいなー。ちんこ、立ってるわ。変チンのポーズ、ここの、みんなに伝えておくから。」
と話した。
それから飛苧が、そのキャバクラに行くと大モテとなった。あるキャバ嬢は、
「波山さん、いつが、お休みなのかしら?」
と聞いたので、飛苧は、
「水曜日が休みですよ。不動産屋だから。」
と答えてしまった。
「そうなの。わたし、リモコンみたいな無線連絡機器を持っているから、それで連絡を送るわ。」
その無線の連絡が、あのビルの谷間の危機だったのだ。
「ほんの、お遊びのつもりが、身の危機を救ったわ。」
と、あのビルの谷間にいたキャバ嬢は仲間に話す。
「そんなら、わたしにも、その無線機欲しい。」
「わたしも、よー。」
「わたしの美貌なら、二台いるかも。」
とワイワイガヤガヤとキャバ譲達は騒ぎ出し、結局全員が無線機を持つ事になった。
水曜日、休みの日は波山飛苧はバイクで福岡市内を走っている。最初の呼び出しでは変チンポーズは慌てていて、するのを忘れていた。あとで、あのキャバ嬢に追及されたが、
「ごめん。でもアレは立ったから、いいだろう。」
と飛苧は逃げていた。
波山飛苧の叔父さんが、沖縄に空手留学して帰ってきたのは、飛苧が二十歳の時だった。沖縄にある空手が日本に全部伝わっている、というのは間違いだ。というより沖縄も日本なので、こういう表現は、まずいのだが。日本本土というのも適切ではないとすれば、沖縄県から日本の他地方とするのが正確だろう。
彼の叔父さんは水剣流という、沖縄から出たことのない流派を学んで来たのだ。
この水剣流という流派は、琉球王朝時代に宦官にする男達の陰茎を、切り落とす時に大いに活躍したと云われている。
宦官とは去勢した男性の事だが、彼らは王様のペットのようなものだったろう。尻の穴も貸していたかもしれない。
宦官志願者は、月のない夜に首里城の庭の一角で陰茎だけ出して、膝を曲げて屈む。中腰の姿勢だ。そこへ水剣流の師範が現れると、左手で宦官志望の男の陰茎を握り、
「えいやっ、きえー。」
と掛け声を掛けて、手刀で(手の指を全部くっつけた形)、小指の下の手の側面を鋭く男の陰茎に振り当てた。宦官志願は、
「ああーっ。」
と声を上げる。男の陰茎は、水剣流宗家の手刀で見事に切り落とされていたのだ。
この水剣流の秘儀に子宮殺し、というものがある。女の子宮にペニスが当たっても、ああ、気持ちいい、と声を出されるだけだが、この流派では宗家は若い頃から、巻き藁に自分の勃起した陰茎を突いて鍛える。やがて、
「おおーりゃあーい。」
という掛け声の下、瓦一枚は勃起した肉茎で割れるようになるという。
ここまで鍛えれば、性交中の女性の子宮を自分の勃起肉棒で突き、死に至らしめることも、あるというのだ。
恐るべし、水剣流空手である。飛苧は叔父さんに、
「おじさんも、その子宮殺しを身につけたのですか。」
と聞いた。四十代の精悍な鼻の下に、髭を、はやした目の大きなおじさんは、
「ああ、日本というか、福岡から、わざわざ来てくれたというのでね、その秘儀も訓練したよ。ただ、瓦は一枚、自分の勃起したやつで割れたけど、実際の女はね、ためしたこと、ないけど。」
「そうだねー。殺人罪に問われるかもね。」
「いや、それは分からないと思うよ。子宮損傷で出血多量になると、死ぬだろうけど。琉球王朝時代は医学も進んでいなかったから、間に合わなくて死ぬ事もあったろうね。でも、今の医学で病院に運ばれたら、助かるんじゃないかな。」
なるほど、と飛苧は思った。
叔父さんの名前は、波山正拳(なみやま・ただけん)という変わった名前だ。これは、叔父さんの父、つまり飛苧の祖父が空手好きで、飛苧の父の兄に正拳という名前をつけたのだった。
叔父さんの波山正拳は福岡市内、南区に道場を構えた。三百坪の敷地に道場を作って、弟子を募集した。道場は、やがて、人が大勢来たが、女子大生も大学の空手部だけで飽き足らずに入門する事もあった。そんな、或る日、
入門したばかりの女子大生が、頬に切り傷を、つけて道場に来た。正拳師範は、
「狭霧君、どうしたのだね、その頬の傷は。」
と道場に上がって空手着を着ている狭霧照子(さぎり・てるこ)に尋ねた。狭霧照子は大学三年生で二十一歳、胸も大きいし、尻も横に張っている。背は百五十五センチだ。
「やられたんです。女のチンピラに。わたし、中洲に飲みに行った時、からんでくる三十位の柄の悪そうな女に、
「しつこいわね。蹴飛ばすわよ。」
と云ったら、
「いい度胸じゃないの。やってみらんね。」
と言われたから、カウンターの椅子に座ったまま、右横の、その女の膝を蹴ったんです。そしたら、どーん、と、その女は椅子から転げ落ちました。軽く蹴ったので、骨に別状は、ないと思いますけど、
「あいたたたたたーっ。骨が痛い、よくも、やったな若造め。」
と言いながら、苦痛に顔をしかめて、そのチンピラ女は立ち上がると、飲んでフラフラしているわたしに、ポケットから何か出して切りつけたんです。それは、剃刀でした。それで頬を切られて・・・。
なおも、切りかかろうとする女を店の用心棒が抑えて、それで終わったんですけど。」
正拳師範は静かに聞く、
「中洲の、なんという店かな。」
「朝まで昼顔、という店です。」
「ようし、必ず仇は取ってやるからな。」
正拳師範は、腕を組んだ。
中洲の「朝まで昼顔」という店を正拳師範は、すぐに見つけた。中に入って、何やら話しをていたが、あのチンピラ女の事が分かったらしく店を出てきた。夕方の四時だ。
正拳は中洲の橋を渡って、公園のベンチに腰を下ろした。目の前に生命保険会社がある。
期待に胸を、ふくらませたアナタを見たい 福福生命
という看板も出ている。午後五時になった。その生命保険会社のビルから出てきた女の一人を認めると正拳は立ち上がり、すすーっと氷の上を滑るように女に近づく。三十代の女で、大柄だ。しかし、胸も尻も小さい。頭はパンパーマをかけていた。
正拳は、
「ちょっと、待たれい。」
と声を、その女に、かけた。女は立ち止まると、
「何か、御用ですか。生命保険加入の事でしたら、ここでも承ります。」
女は低い鼻を膨らませて答える。
「いいえ、そうでは、ありません。あなたのご乱交について、責任を取っていただく必要が、あります。」
女はキョトンとして、
「なんの事でしょう?何か、よくわかりませんけど。」
と言うと、外交員が、よくする微笑を浮かべた。
「わからないのなら、教えてあげますよ。こちらに、いらっしゃい。」
正拳は女を手招きして、人の通りからは見えない大樹の陰に、女を連れて行った。
大樹に背中を向けた大女は、歩道や車道からは見えないようになった。公園にも寒い日なので、人は一人も、いなかった。川は福岡市の河口に近く、少しの幅がある。四十メートル程の川幅で、ひんやり、とした冷気が公園の中に漂っていた。
大女は再び、
「なんの事ですか。」
と言うと、パンチパーマの髪を右手で撫でた。正拳は、
「秘儀、全髪落とし。」
と声に出すと、大女の髪の毛に両手を当てて素早く髪の毛を大量に引き抜いていった。
「ぐわわわっ。」
女はバッグの中から何か、取り出すと正拳に向けた。正拳は、
「そうは、いかのきんたまだ。それ。」
と足で女の右手を蹴った。剃刀は女の手から飛んで、女の頬に当たり、女の頬からは血が流れ出した。正拳が手を止めると、女の髪の毛は三分の一、両耳の上だけ残っていた。
「なんてこと、するんだー。」
と喚きながら、女は正拳に掴みかかってくる。その女の手の手首に、正拳は手刀で打撃を与えた。女は右手を押さえて、
「いたーい。手が痺れて動けない。どうして、わたしが・・・。」
「おぬしは、わたしの弟子の女子大生の頬を、剃刀で切っただろう。傷害罪で警察に届けない代わりに、こうしておけば、弟子も満足すると思ってな。」
「あの女は保険の勧誘を簡単に断ったんだ。親切に説明したのに・・・。」
「ばかものっ。保険など、今は、いくらでもある。」
「それは知ってるよー。でも、ぶらぶらと旦那は遊んでいるんだ。稼がないと・・・。」
「たわけがっ。」
正拳は、女のスカートを、めくりあげると、ショーツを指で掴んで引き裂いた。股間は、かなりな剛毛だった。
「上の髪の毛も少し、残してやった。下の毛も少しは残してやる。」
正拳は、そう話すと、グイと大女の陰毛を掴み、一気に大量に引き抜いた。
「あわあー、パイパンに、なるう。」
女が叫んだが、女の陰毛は髪の毛と同じく、両脇は生え残っていた。正拳は、
「今後、何か少しでも私の道場生に手を出すと、次回は、これくらいでは、すまさないよ。」
と言い置いて、ゆっくりと緑の芝が生えている公園を出て行った。
波山飛苧には、このような叔父さんがいる。女子校生のキャバ嬢を助けられたのも、水剣流空手を幾分か習得していたためだ。
不動産業界は二月と八月は暇だ。だからといって、店を出るわけにもいかない。八時前には店のシャッターを降ろし、中洲に飲みに繰り出す。行きつけは、キャバクラ「女子校生」だ。セーラー服のキャバ嬢が酒を注いでくれる。そのうちの一人が、暴漢に襲われそうになった何子(なんし)だ。英語の女性名、ナンシーから、つけられている。
何子は他のキャバ嬢達に、
「波山さんに助けられたのよ。危うく、襲われるところだった。」
と話すと、
「よかったわねー、どうやって、助けられたの?」
と聞かれたので、
「無線で呼んだのよ。そしたら、近くをバイクで走っていたらしくて、来てくれて。かっこよく、暴漢を倒したのよー。」
「すっごーい。わたしも無線機、持ちたい。」
「わたしも。」
「わたしもねー。」
「ミー、トゥーです。」
という感じで、そこのキャバ嬢は全員、波山飛苧に連絡のつく無線機を、持つ事になったのだ。
そのキャバクラの経営者、楽田繫栄(らくた・はんえい)は福岡市内の、あるビルで乱交パーティを企画した。インターネットで参加を募ると、意外にも女性は、すぐに集まったが、男性は誰も参加してこなかった。
五十歳の楽田は鼻の下の髭を、右手でいじりながら、
「困ったなあ・・・。普通は逆だと思うのに。」
と独り言を言った。
その場には、数人のキャバ嬢が、いた。事務所みたいな部屋だ。一人のキャバ嬢が、
「波山さんに来てもらえば、いいんじゃないですか。二月の今は、不動産業界は暇らしいですよ。」
楽田は眼を輝かせて、
「そんな人、いたのか。ぜひ、誘ってみてくれ。」
「はい、わかりました。やってみます。」
その日、誰も客が来なかった不動産仲介の店を、出た波山飛苧の携帯電話が鳴った。
「はい、もしもし。」
「波山さんですか。キャバクラ女子校生の、江真(えま)です。」
「ああ、どうも、久し振り。」
「波山さん、困っているんです。助けてください。」
店の前は人通りも少しあるので、近くの小さな公園に駆け込むと、飛苧は、
「どうしたのかな、急に。」
「実は、うちの社長が乱交パーティを企画したんですけど、男性が集まらなくて。」
「そんな事、言ったって、こっちも、そんなものに参加した事ないからね。」
「そこを一つ、よろしく、お願いします。」
「困ったなあ。ぼくも、もう四十だし、何人もの女性とセックスをするのは体が持たない気がする。」
「派面ライダーに変身したら、どうですか。」
「うはははは。そうだね、考えてみるよ。」
「じゃあ、日時は追って連絡しますから。」
「おい、ちょっと・・・。」
プツ、ツー、ツー、ツー。と携帯電話の通話は一方的に切れていた。
一人で部屋に帰った飛苧は、電燈のスイッチの紐を下に引くと、
「乱交パーティと、いったってなー。」
と溜息をついた。それからノートパソコンを起動して、アダルトDVDを入れて見始める。それは乱交パーティのAVだった。四つん這いに、ベッドの上で構えている裸体の女性に中年男が後ろから、挿入した。悶え始める女。男の顔は無表情に仕事をしている感じだ。
「柵城(さくしろ)!こんなところに、出ていたのか。」
飛苧は一人で叫んでしまった。その男は小学校高学年の同級生、柵城・滝輔(さくしろ・たきすけ)だったのだ。
柵城と会わなくなって久しい。が、ネットで調べれば分かるかも、と思い飛苧はパソコンで検索した。
AVでは珍子・出酢蔵(ちんこ・だすぞう)という名前で画面には出ていたが、本名で調べたのだ。
あった、と飛苧は喜びに胸を躍らせた。なんと奴は、無料ブログで実名で書いていたのだ。そのタイトルも、
AV男優の孤独
顔写真はブログには付けていないので、珍子出酢蔵と気づく人は、ほとんど、いない筈だ。
日記風の文を読むと、
今日は本番撮影が二本あった。昼と晩。一発ずつ、射精して終わった。監督に、
「二発は出さないと駄目だ。」
と云われて悩んでいる。何か、いい方法ないですか。レビトラ、シアリス、バイアグラとは別のものが知りたい。
いいコメントを、くださった方には、心ばかりのお礼を差し上げます。
と書いてある。
本人にメール、も、できるようだ。インターネットとは、かくも素晴らしい。柵城、待ってろよ、おれが今、メールするからと飛苧は心ワクワクさせて、
柵城君、ぼくだよ。小学校の頃の波山飛苧だ。もっとも波山は学年でも、おれ一人だったから分かるだろう。暇なとき、福岡に来ないか。できれば、大至急。
いい話が、あるんだ。
そうキーボードで打つと、そのブログを通じて柵城滝輔に送信した。
次の日、退屈な不動産会社から帰宅した飛苧は、ノートパソコンのメールボックスを真っ先に起動させた。
柵城滝輔からの返信が、あった。湖に太陽が浮かぶような希望が、飛苧の胸に満ちる。
久し振りだな、波山。おれたち小学校四年の頃、商店街の道をチンコ出して歩いた事も、あったよな。おれは、だから今の仕事をしている、といえるけど、君は何をしているんだ?
ひまは今度、三日くらい休めるから、福岡に行けるよ。
飛苧は楽しくなって、返信した。
おれは不動産屋だけど、今、ひまなんだ。新幹線で来るんだろう。迎えに行くよ。
思ったとおり、柵城は新幹線で来福する、とメールを出してきた。そこには携帯電話の番号もあったので、飛苧は自分の携帯から電話した。
ただ今、留守にしております。発信音の後に・・・
プチ、と飛苧は携帯電話を切ってしまった。AVの撮影中か・・・と思いを巡らせる。柵城は珍子・出酢蔵として、仕事中なのだ。
新幹線から博多駅に降りてきた柵城は、とても疲れた顔をしていた。飛苧は手ぶらの彼に近づくと、
「元気、なさそうだな。」
天井がある新幹線のホームで、再会の言葉を発すると、
「うん。毎日立たせていたからな、ムスコを。」
「よし、それじゃあ、うまいものでも食べに、いこう。」
「そうだね。おごって、くれるのか。」
「無論、おれの、おごりだ。」
飛苧は博多駅に隣接したビルの食堂街に、柵城滝輔を連れて行く。ウェイトレスは二十代前半の巨乳、巨尻で、引き締まったウエストの女性だった。眼は、まん丸で、髪は肩までの黒髪、注文を聞きに来た時も、座っている二人に身をかがめると、彼女の胸と尻は色っぽく弾んだ。
その店はフランス料理の店だった。飛苧はメニューを片手に、
「昼のスペシャルにしよう、いいな?柵城。」
「それに、してくれ。」
と答えた彼の視線は、ウエイトレスの胸と尻を眺めていた。
柵城はウエイトレスが向こうに行ったので、飛苧に向き直り、
「昼のスペシャルって、いくらなのかい?」
「三千円だけどな。」
飛苧は、ゆとりを持って答えた。柵城は驚くと、
「随分、高いな。金もちに、なったね。」
「いや、福岡市は他が安いからね。」
とはいえ、フランス料理店は福岡市にも数えるほどしか、ない。そして、それらの店は安いということは、ない。柵城は、うなずくと、
「そうだなあ。福岡市は家賃は安いね。ぼくなんか、東京でも中野に住んでいるから家賃も高いね。AV男優だから、メーカーの事務所に近くないと、大変だから。
一ヶ月住むために、八人の女と、しなければね。」
「八万円、か。」
「そうだね。一万円以上、もらう事も、あるけど、安く多く、やりまくらないと、いけないんだ。」
「ほおう、でも女が好きなら、それで、いいねー。」
「仕事にすると、きついな。常にチンコの先には、ゴムが乗っているものね。」
「時々、コンドームを外したくなるんじゃ、ないか?」
「それを、やれば、即クビだろう。今の時代、他に仕事もないし。AV男優もやっていると、精力剤のキャラクターに使ってもらえるし、本業以外の収入もあるんだ。そのイメージキャラクターには、サングラスかけて出たから、顔は知られなかった。珍子・出酢蔵という名前は出たけど。AVを見ている人は、案外、男優の名前は気にしないもの、だからね。博多駅でも、誰も、ぼくの顔に気づかない。」
「女の体と顔ばかり、見ているからな、AVでは、男は。」
出されたスープを見ると、柵城は、
「遠慮なく、いただくよ。」
「ああ、どうぞ。」
と、うなずいた飛苧に、
「話は変るけど、さ、東京でインターネットで見たけど、福岡に派面ライダーって、出没するそうだな。」
「・・・・・、そうか?知らないけど。」
「アイマスクみたいなのを、つけて、出てきて女を助けるそうだな。目撃証言が、あるよ。」
そう、あれから又、キャバクラ女子校生の一人が、中洲の裏道で暴漢に襲われそうになったのだ。しかも、火曜の夜遅くに。だから近くで飲んでいた波山飛苧はポケットの通信機がバイブレーションしているのに気づいた。
サングラスを掛けた三十半ばで背広、赤いネクタイの長身の男が中洲の裏道で、セーラー服の女性を後ろから抱きすくめていた。男は女性の髪をペロリと舐めて、セーラー服の上着の上から、女性の乳房をムンズと掴んだ。
「あはっ、やめてー。」
いやいや、ながらも少し感じた女は声を上げた。でも、嫌悪感が強く走る。
「おい、おまえ女子高生なんだろ。こんなに遅い時間に、中洲を制服で歩きやがって。おれのする事に文句つけたら、学校に言いつけてやる。」
「わたし、学生じゃないのよ。キャバクラに勤めているの。」
スカートの尻を触られながらも、若い女は、抗議した。
「ふん、うそを言うな。ビルの陰で立ちマンしてやるぜ。セーラー服の女に立ったまま、入れてみるのが、おれの、したい事だったんだ。」
女子校生は右手で、なんとか、リモコンみたいな無線機のボタンを押した。
「助けて!派面ライダー!」
女は声を限りに叫ぶ。男は女子校生の股間を、スカートの上から撫で回して、
「おいしそうな、マンコだな。指に吸い付くような感触。派面ライダー?なんだ、それ。」
その時、軽二輪の走ってくる音が、した。二人は顔を、そこへ向けると、右目にアイマスクをした男が白バイの警官の制服を着て、オートバイに乗っていた。ただ、赤色が、あるのが白バイ警官の制服との違いだ。
セーラー服の成年女性は、彼を見て、
「わーっ、派面ライダー、来てくれたのね。」
と黄色い声をあげる。
バイクは止まると、派面ライダーはジャンプして、男の顔面に蹴りを入れた。
「うがあっ。」
サングラスを落として、男は道に倒れる。そのまま、気絶したようだ。女子校生は派面ライダーに駆け寄り、抱きついた。
「ありがとう、派面ライダー。」
「いいえ、どういたしまして、ね。引越しの時は、・・・いや、さらば、です。」
「いかないで。お礼は、わたしの体で、します。」
「いいですよ、そんなのは。わたしは正義の派面ライダー。」
「ビルの陰で立ったまま、はめて。」
「えっ、いえ、そんな・・・。」
「お礼は、受け取るものよ。派面ライダー。」
「わかりました。ごっつあん、しようかな、いただき、まーす。」
アイマスクをしたまま、派面ライダーと女子校生の姿の成人女性は、ビルの陰に入り、奥まで行くと抱き合い、キスをした。女は派面ライダーの股間を、待ちきれないように探ると、
「あれ?まだ、立ってないわよ。」
と咎めた。
「悪いねー。今、立たせるよ。」
派面ライダーは謝ると、両手を、手のひらを向き合わせた形で、真っ直ぐに上に挙げた。
「変チン、」
「おおーっ。」
派面ライダーが両手を下に降ろすと、彼のモノを握っていた女子校生は、
「きゃあ、立ったわーっ。」
と喜びの声を上げる。
派面ライダーの淫欲の棒は最大限に膨張していたのだ。
女は彼のジッパーを下げると、太くなったモノを取り出し、自分のショーツを膝まで下げて、自分の股間の淫裂の谷間に、それを自分で埋め込んだ。
「ああん、いいわーっ、派面ライダー・・・・。」
セーラー服を着た成人キャバ嬢は、突き出た尻を激しく前後に揺らせていった。もちのような彼女の膣内の肉が、派面ライダーのチン肉に絡みついて離れない。
彼の両手は、セーラー服の上から乳房を握り、上下に軽く揺すった。
「いやあああん、強い男って素敵!」
女子校生姿の美女は、ビルの壁に手をついて、激しく悶えた。
三十分後、派面ライダーは彼女に、膣内射精して終わった。萎えたモノをズボンにしまうと、
「さらば。又、呼んでね。」
と一言残して、250CCのバイクの轟音を響かせて、ビルの森に消えていったのだ。
柵城・滝輔はポカンとしている波山飛苧に、
「おい、どうしたんだよ。眼が、ガラスの玉みたいだぞ。」
と指摘する。飛苧は頭を軽く振ると、
「あ、なんでもないよ。派面ライダーって、面白いね。」
と作り笑顔を浮かべた。
六千円の会計は、飛苧にとっても痛いものだったが、食後のコーヒーは黒砂糖の丸玉を入れて、飛苧は、
「実はね、福岡市内のビジネスホテルで、乱交パーティの企画が、あるんだよ。女性の方が集まったけど、男性は一人も参加者が、いない。さすが、福岡だね。」
と切り出した。柵城は動じずに、
「そうか、福岡では珍しいんだろうな。そういうのは。東京では、日常的に行われているよ。おれもAV男優だから、呼ばれる。それがね、一般的には募集されない事も、あるんだ。例えば、芸能プロダクションの売り出し中のアイドルだけを集めた、乱交パーティとかも、ある。そんなの、一般に知られたくないだろ?」
「ああ、そうだね。第一、考えられないな。」
柵城はフフ、と笑うとコーヒーを、がぶ飲みして、
「最近アイドルと言っても量産というか、メンバーが多いと言うか、おれも一人で捌けないので、三人くらいのAV男優で、やってるよ。向こうが九人で、おれたちに三人ずつ、列を作って水着で立っている。みんな、プリプリの、おっぱいをビキニで隠しているけど、背中で紐を結んでいるだけだから、両手を回せば、すぐに取れるよ。
アイドルも貧乳の子とかは、こういうのに回って、こないんだ。つまり、彼女達が同業者と熱愛の仲に、なったりしないようにAV男優の、おれたちで、彼女達の性欲を満たしてやるわけだ。テレビとかに出ている可愛い子も、三人くらい、一遍にハメまくったよ。大抵、処女なんて、いないから、その点は安心だ。
中には、おれを仰向けに寝かせて脚を開いて跨り、ロデオの馬に乗っているように、激しく腰を動かすアイドルもいた。
特にね、テレビドラマとかでイケ面俳優と共演が決まると、芸能事務所は毎日のように共演しているアイドルをおれたちにセックスさせて、その俳優に恋をしないように、させているんだ。そんなの、信じられないと思うけど、ドラマは、あくまでも虚構で、あるわけ、なのに主演男優にメロメロになったアイドルが過去にいた。イケ面男優もゴシップを怖れて、共演アイドルには手をつけない。そのアイドルは巨乳だったけど、彼女の事務所はAVにも関係していたから、そこのAV男優三人に、一度に代わる代わる、ハメさせたんだ。
まず最初の男優は正常位、次は後背位、最後の男優は騎乗位だった。それで男優はゴムつけて、中出し、したんだけど、最後のセックスは、巨乳アイドルがリードしていて、三時間も乗られ続けたんだって。
その巨乳アイドルが、そのドラマに出る日の前の晩は、AV男優は忙しかった。とうとう、ぼくのところにも出番が来てね。その巨乳アイドルをビジネスホテルで三時間位、ハメたんだけど、キスするだけで乳首は立つし、眼は潤んで股間のマンコも濡らしているんだ。テレビドラマで、イケ面俳優とのキスシーンの時の事を聞いてみると、
「ああ、あの時、わたし、乳首も立っているし、まんこも濡らしているの。でも、撮影スタッフは気づかないわね。あのイケ面も気づいてないわ。舌を入れてやろうとしても、あいつ、唇を開かないのよ。イケ面の股間にスカートの上からでも、わたしのマンコを押し付けるけど、チンコ立てないのよ。あいつ、インポなのかしら。でも、前の晩、あなたと激しくセックスしているから、それ以上、燃えないで、すむわ。もし、あなたとセックスしていなかったら、あのイケ面のチンコ、握っているかも、しれない。」
と答えてくれて、硬く尖った乳首、それは黒ずんでいるけど、を、おれに吸わせてくれたんだ。
アイドルって淫乱なんだけど、茶の間の人や企業のやつらは気づかないね。しまいにはホテルで窓を開けてセックスしたい、って言うんだ。だから七階の窓を開けて、裸のアイドルを後ろから挿入して、突きまくった事もある。そのアイドルは、それからテレビのコマーシャルに出て、笑顔で写っていたけど。
テレビとかでは、ていねいに落ち着いて喋るけど、おれとのセックスの時は、
「おまんこの奥まで、ずんずん、ズームインしてっ。」
とか、叫ぶんだ。」