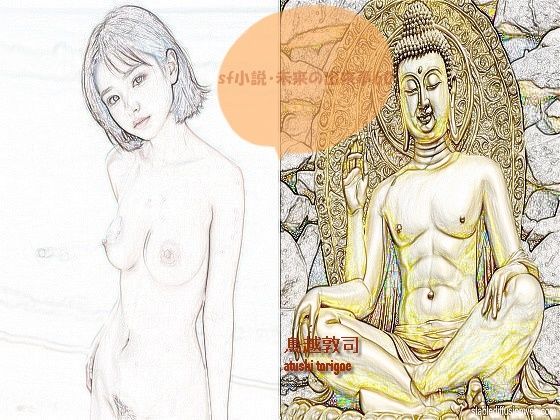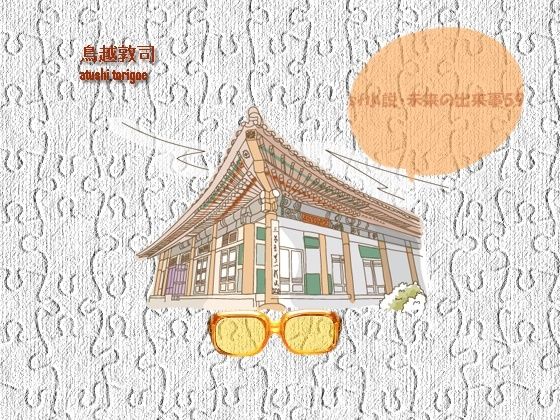尼野影子は日曜までに身の回りのものや衣服も処分して、身一つで尼僧院に向かった。
尼僧院の受付で、
「得度式を受けに来た尼野と申します。」
と影子は話すと尼僧は静かな微笑を、たたえて、
「お待ちしておりました。院長は準備を整えております。私が案内しますから、ついて来てください。」
と答えると立ち上がった。
広い境内と長い廊下。枯山水の庭園。尼僧が案内したのは大きな金色の仏像のある部屋だった。床は板張りで仏像の股間には何と大きな男性器が露出している。
それを見た尼野影子は眼を、ひそめた。女院長は影子の視線を捉えて微笑み、
「仏像に性器があるのを奇異に思ったのですね。」
と立ち止まっている影子に聞いた。
「はい・・。変わった仏像なのでは・・・。」
尼僧院長は誇らしげに、
「もちろん、とても変わっています。いえ、ほとんどの尼僧院だけでなく僧院にしても男性器のある仏像は日本には、ないでしょう。でもチベットなどでは昔からある僧院もあります。いずれにしても尼僧として貴女も男との縁を切って生きて行くのですから、男性器にも無感覚とならなければ、なりません。」
「はい、院長様。そのように、いたします。」
と影子は、しおらしく答えた。
「よろしい、それでは得度式を行います。その前に尼野さん、あなたの豊かな黒髪を総て切り落としますよ。いいですね?」
「はい、分かっております。」
と素直に答える影子。
部屋には数人の尼僧が入ってきて影子の服を白装束に着替えさせた。それから影子を正座させると、一人の尼僧が電動バリカンを影子の頭に構える。尼僧はバリカンを持つ右手を離した。空中に浮いた電動バリカンは、とても巧みに影子の長い黒髪を刈り落としていったのだ!
全自動・電動バリカンである。
バリカンの中に人工知能が埋め込まれていて、カメラアイで影子の黒髪の頭を捉えて、人の手を借りずに刈り上げて行く。
影子は、それに気づく事もなく彼女の頭の長い黒髪は全て刈り落とされた。
剃髪を終了した全自動バリカンは影子の丸坊主の頭の斜め上に静止した。尼僧は、それを掴むと尼僧院長に向かい、
「院長様。終了しました。」
「よろしい。それでは授戒、法名を授けます。その前に大仏様を礼拝して、読経をするのです。」
という事で影子は金色の大きな仏像の前に正座させられた。さっき見た時より、仏像のスグ目の前に座っている影子は仏像の股間の露出した男性器をアリアリと見てしまった。
半勃起しているかのような男性器で、ある。
近くに立っている尼僧院長は影子の横に座ると、
「このように礼拝しなさい。」
院長は正座のまま深く頭を下げると両手を前に伸ばして床に付ける。それから上体を上げて元の姿勢に戻った。
影子は、それを見ると同じように上体を深く前に倒して両手を伸ばして床に付けて金色仏像を礼拝した。
横にいる院長は経本を手に持ち、読経した。そのあとで経本を影子に渡すと、
「それを私のように声を出して読むのです。」
影子は読経した。
尼僧院長は、
「よく出来ました。」
と話すと立ち上がり、影子の前に立つと、
「五つの戒を授けます。不妄語、不偸盗、不邪淫、不飲酒、不殺生。意味が分からなければ、後で教えます。アナタの法名は春恵(しゅんけい)。さあ、春恵、立ち上がって大仏様の前に進みなさい。」
指示された通り、春恵は立ち上がり、金色仏像の前に進んだ。尼僧院長は、
「大仏様の前に座り、股間の珍棒を口に含むのです。」
金色の仏像だけに股間の半勃起棒も金色だった。
春恵は、(え!?)と思ったが言われた通りに金色仏像の前に座った。金色の半勃起棒が近くに見える。
院長は、
「どうしました、春恵、早く大仏様の金色棒を口に。」
春恵としては尼僧になって、そのような事をしていいのかと思ったが院長の指示だから、と顔を近づけて金色半勃起棒を口に含んだ。すると、その大仏の股間棒は膨張を始めて勃起した。
春恵の口の中で固く勃起した大仏の股間棒だ。影子としては今までフェラチオというものを、した事がなかった。
尼僧に出家して、まず、この金色の大仏の股間勃起物を口に咥えるとは・・・。その硬さが影子、今は春恵の口の中では人間の男の男根を感じさせ、膣内に入っている時を思い出させた。それで春恵はオマンコに入れられている感覚を少し味わったのだ。
男との関係を断ち切っても大仏様が存在した。ここは普通の尼僧院では、ないと思うが、こうなったのも何かの縁だと春恵は思った。
金色仏像の股間棒を口に含んでいるとオマンコが少し濡れたのを感じた。そこに尼僧院長が、
「はい、そこで停めて。口から大仏様の珍棒を外すのです。」
と命じたので春恵は言われた通りにした。
こうして尼野影子の得度式は終わった。
尼僧院長の法名は春珍(しゅんちん)と言う。年齢は30才と若い。実家は古くからの寺院で、小さい頃から父親に仏教を学び、仏教系大学で仏教学修士号を取得したのちにチベットの僧院に入ったのは24才の年だ。ゲルク派のチベット密教寺院のためか性に寛容な場所であった。
六年間も、そこで修業を積んで日本に帰り、この尼僧院、金仏寺の住職、すなわち尼僧院長になった。すでに、その尼寺には数人の尼僧が、いた。が春珍が僧院長となってから急速に尼僧に出家する事を希望する女性が増えたのだ。
従来の尼寺では男との縁切りとして尼僧になる場合が、ほとんどである。が、しかし、そこはチベット密教の尼寺のため、永久に男を絶つわけではない。
院長の春珍も三十歳にして男を知った。チベットの寺院での修行を終えた後で、そこの寺院の男性僧侶と大仏像の前で交わった。相手の男性僧も三十路男で独身である。
その大仏像も対面座位で裸身の女と性交している姿なのだ。
春珍は何度も快楽の極楽に昇りつめた。チベット密教を修行してきて良かったと思ったのだ。
相手の男性僧にしても同様な思いで独身で僧侶の為に女との接触は一切ないため、有り余る精力を保持していた。という事で春珍尼僧院長も男を知っているのである。
尼寺に駆け込んでくる女性は男性との縁を絶ちたいという事が理由の最大である。という事は既に男性と関係していて、その関係を絶つのが尼僧になる理由だ。
そういう事からも尼僧院長が処女である事は尼寺の運営にも喜ばしい事では、ない。
春珍が院長になってから尼僧院も円滑に運営された。厳しい修行も男性との縁を絶つためと思い、修行に明け暮れる尼僧達だったが、或る日、春珍の部屋に一人の尼僧が来て、
「院長様。同室の永聴についてですが。」
と困ったように報告する。
春珍は机の上から目を上げて、
「どうしたの?永夏。」
と応じた。永夏という若い尼僧は、
「この頃、毎晩、永聴はオナニーするんです。布団に入ってからですけど。声を抑えていますけど、聞こえます。時に、大きな声で感じた通りに悶えるんです。院長様、どうしたらいいのでしょうか?」
と訊くと春恵はフ、と笑みを浮かべて、
「永聴も、まだ25歳。尼僧になるには早すぎたわ。させておきなさい、永夏。永夏も26歳なら、男が欲しくなるかもよ。」
と諭した。永夏は口を尖らせて、
「いいえ、わたしは。院長様、別れた旦那はセクシー男優でしたから朝、昼、晩、求められました。
もう、ああいうものは、いいんです。」
「別れた原因は、なんだったの?」
「旦那が本番の撮影の毎日で、しかも、その日は相手のセクシー女優の部屋に泊まり込んで帰らなくなったんです。そのうち、そのセクシー女優が旦那の子を妊娠したからなんですけど・・・。」
「永夏は子供は、いないのね?」
「いません。旦那とはコンドームつきの交わりでした。それというのも射精を、こらえて次の日の撮影に備えるためというんですから改めて腹が立ちます。」
と話すと怒りに肩を震わせた。
春珍は宥め顔で、
「もう過去の事は忘れなさい。それも仏様の導きです。厳しい修行の後には再び、いい男性と巡り合えるかもしれない。そこが他の尼僧院とウチが違う所です。」
「再び、いい男性と・・・ですか?」
「ええ、そうです。修行の成果次第で再び、男と出会えるようになります。ウチはチベット密教ですから男女の交わりを拒否しません。」
と春珍院長はキッパリと宣言した。永夏は目を丸くして、
「チベット密教は、そういうものなんですね。私は尼寺は何処でも同じだと思っていました。」
「かなり違うと思うわよ。男との縁を切るためなのが日本の尼寺ですけどね。ウチは違います。
チベット密教の秘法、処女に戻る法もあるの。永夏の修行次第で、その法を教えられる。」
「処女に戻れるんですか?」
「処女膜も含めてね。精神とかだけ戻っても意味ないですよ。仏教には女体に男性器を発生させる法もあるから、処女に戻るなんて、それほど難しくは、ないけど簡単でもないわね。修行の成果次第だわ。」
永夏は更に目を丸くして、
「凄いと思います。チベット密教は。」
「でしょう?それでは就寝前の瞑想も熱心にする事です。」
「はい、院長様。失礼します。」
永夏は尼僧院長室を出た。
院長の部屋にはチベット密教の様々な仏、菩薩の像が置いてある。それは観賞するためでなく、礼拝するためのものだ。
歓喜天の結合姿の像もある。
春珍はチベット密教寺院で処女を捨てた。ここの尼僧院の院長になる前に処女膜を再生させた。それは無論、医学によるものではない。
観想と体操、そして特殊な食事が必要だ。そして或る菩薩に祈る事である。
すると一週間後に春珍の処女膜は再生していた。
そこの尼僧院では同性愛は禁じられている。それは邪淫であるからである。それは春珍も厳重に指導した。
今日も寝床に入ってから尼僧、永聴はオナニーに耽っている。彼女は元々、バスガイドだった。長距離旅行のバスのバスガイドで、よく同じバスに乗る運転手と恋愛になり、結婚した。結婚前から肉体関係が出来たが、いつも同じバスに乗る訳ではないために、長い間、会えない日も続いた。
そんな時の夜は女子寮の部屋で、交際相手のバスの運転手を思い浮かべてはオナニーに耽ったものである。
恋人の勃起物と同じ長さのバイブレーターをネット通販で購入して使用する。バス会社の女子寮だが個室なのでバイブレーターを使ってのオナニーも誰にも気づかれないものだった。
その恋人のバスの運転手は別のバスガイドと共に富士山の方へ観光バスを運転して移動していた。
法名、永聴、俗世での名前は永子、という。
その恋人のバスの運転手は別のバスガイドとホテルに泊まっていた。もちろん別々の部屋だったが、運転手の部屋に美人バスガイドがドアを開けて、
「春埼さん、入っても、いい?」
と聞いた。
「ああ、いいよ。どうぞ。」
美人バスガイドは部屋に入り、運転手の春埼の近くに座ると、
「永子と、付き合っているんでしょ?いいの?わたしを部屋に入れて?」
「ああ、いいんだ。永子とは軽い付き合いだから。」
「そうなんだ、真剣交際かと思ってた。」
「いやー、永子より君の方が美人だよ。」
「まあ、嬉しい。わたしも、そうだと思っていたけど。」
二人は抱き合い、キスをした。
美人バスガイドは、
「こんな事、してもいいのかしら?永子に悪いわ。」
「いいんだよ。永子とは別れようと思っていた。ちょうど、その時、君が現れたんだ。」
「グッドタイミングって奴ね。今からセックスして、それを撮影して永子に贈るの。そうしたら永子はアナタと別れるわ。」
「グッドアイデアだね。スマートフォンで自撮りするかな。」
「そうね。わたしのスマートフォンは最新のカメラ付きよ。立体映像を撮れるの。録画再生するとスマホの画面から映像が立体的に飛び出してくるわ。」
「ほー、すごいな。じゃ、この部屋でセックスして、それを最新式カメラで自撮りして、永子の奴に送ればいい。」
「そうね。さっそく脱ぎますわ。」
「僕も脱ぐよ。」
二人は昼は観光地をバスで巡り、美人バスガイドが乗客に観光ガイドした。
「みなさま。左手に見えますのが富士五湖で、ございます。」
美人にして美声の観光案内だった。
運転手は時々、横目で美人バスガイドの尻を眺めては少し勃起しつつ観光バスの運転を続けた。
それで午後四時ごろに大きなホテルに到着して観光客はチェックインして解散した。
二人は同時に全裸になる。運転手は惚れ惚れと美人バスガイドの裸体を見て、
「姫子。すんごい乳房だね。白桃のような乳房だ。」
「ウフ。前の彼氏にも、よく言われたの。その彼とは一晩に五回はセックスした事もある。」
「同じ会社の運転手?」
「そう、けど彼は別のバス会社に行ったから、わたしと会わなくなったの。」
「そうだったのか。」
運転手の股間のモノは半勃起した。美人バスガイドの股間の黒い部分を見たからである。
「田空さん、半分勃起したわ。」
「姫子に見られて恥ずかしいけど、君のアンダーヘアが悩ましくて。催したんだ。」
「田空さん、おっぱい触って。」
観光バス運転手、田空は美人バスガイド姫子の白い乳房を触り、揉んだ。
「あはっ・・気持ちいい・・。」
姫子は目を細めて言う。
田空は、
「最新カメラで自撮りするのは、どうする?」
「あ、忘れてた。今、用意するから。」
姫子は全裸のまま、自分の脱ぎ捨てた服からスマートフォンを取り出してカメラに切り替えるとベッドサイドテーブルに置いた。それから撮影開始ボタンをタップする。
「これで撮影開始よ。」
姫子は高らかに宣言した。
観光バス運転手と観光バス美人ガイドとのセックスは撮影されていく。
昼間に乗客に見せていた姿からは想像も出来ないほどの荒々しいセックスを繰り広げて行く二人。
姫子は口を大きく開けて赤い舌を出した。
コンドームなしの性交だけに通常のアダルトビデオより生々しい。
正常位セックスの後で後ろからハメる座位に移行した後で運転手の田空は連続放出した。
それらはスマートフォンの最新式カメラに逐一記録されたのだ。
二人は翌日、何事もなかったように観光バスの仕事をした。
観光ツアーは三泊四日なので、まだまだ続く。
仕事が終わり、夜が来て、運転手の田空の部屋に美人バスガイドの姫子が来た。
そして又、カメラに交接の記録を取る。次の日の夜も同じ事を繰り返した。それが三泊目で性交を終わらせた田空と姫子はカメラが気になる。田空はベッドに寝そべってタバコを吸いながら、
「うまく撮影できているかな?」
と問いかけると全裸の姫子はスマホカメラを停止させて、
「撮影したものはスグに見れるわよ。」
録画再生を、した。
平凡なアングルとはいえ男女の生々しい交接が記録されていた。田空は、
「よく録画されているな。立体映像になるのでは?」
「ええ、ボタン一つで。」
姫子はスマホを操作した。スマホの画面から飛び出した映像は立体的に見えた。姫子は、
「この機種じゃないと立体的に映像が飛び出さないの。永子のスマホの機種、知ってる?」
「いや知らないけど古いものらしかったね。立体映像は無理かもね。」
「このデータを永子のスマホに送るのよ。メールに添付して。」
「ああ、面白いな。永子、驚くだろうな、きっと。」
「永子のメールアドレス、分かる?」
「分かるよ。ぼくのスマホに永子のアドレス、載ってるから。」
「じゃあ、それをワタシのスマホに送って。」
「ああ、送る。」
それで姫子のスマホに永子のメールアドレスが送られた。
姫子はカメラで交接を記録したスマートフォンを手にして、
「あ、来たわ。それでは送るわよ、永子のメールアドレスに。」
彼らの性交映像はメールに添付されて送信された。
バスガイド永子は長距離旅行の観光バスには乗らない方だ。これはバスガイドの希望によって決められる。
だから永子はバスガイドの仕事で外泊した事がない。
その日も早く女子寮に帰っていた。個室で冷暖房完備、風呂付、冷蔵庫、洗濯機付きの申し分のない環境だ。
東京郊外にある女子寮で、永子は外食して帰って来た。
それから暇なのでスマートフォンを、いじってネットサーフィンなど、していたがメールボックスに添付ファイルつきのメールが届いている。
お元気?
お幸せそうね、永子。彼とは、うまくいってる?田空さんと。
ビデオを添付ファイルで送ったから、すぐに見た方が、いいわよ。
という内容だ。
永子は添付ファイルをタップしてビデオを再生した。それを見た永子は顔色を変えて、
「ああー、こんな事ー、してたのねー、二人でー。」
と思わず口走った。
それは永子の恋人、田空と美人バスガイドの同僚、希世姫子とのセックスの連続だったのだ。
永子は見たくないと思いながら見続けてしまった。三時間も見続けると疲れたので辞めた。ビデオは六時間もある。
(田空さんとは別れるわ・姫子の方が美人だし。)
それで春珍の尼僧院に入った永子だった。法名は永聴。厳しい修行が待っていた。滝に打たれて山を歩く。
瞑想の日々。田空とは結婚していなかったから良かったのかもしれない。
修行が一段落すると女としての欲望が漲ってきた。
寝床でオナニーを始める。同室の永夏に、それを聞かれたかもしれないと思う。
永夏としても男が欲しくなくなった訳ではない。それだけにオナニーに耽る永聴が、わずらわしかった。永夏などはアダルト男優と結婚していた位だ。
話して聞くと永聴は結婚していなかったらしい。
それでも男が欲しくなる、結婚していた永夏は、それ以上に男が欲しくなった。
ついに我慢しきれなくなってネット通販でアダルト雑誌を購入した。そこには色々なアダルト男優の顔が載っている。
その中で気に入ったアダルト男優の顔をハサミで切り取る。
それを観想、礼拝用に持っている仏の肖像画の顔に張り付けると、晩にトイレに入り、それを見てオナニーに耽ったのだ。
同室とはいえ、一人は布団の中で、一人は厠の中でオナニーに耽る。これも通常の尼僧院なら咎められる所を、この春珍の尼僧院「快楽解脱院」では咎められる事は、なかった。それは、ここ快楽解脱院がチベット密教の寺院であるからだ。
修行さえキッチリとすれば時間外は院長の春珍は問わない方針だ。ただ尼僧同士のレズ行為は禁止とした。
ある講義の場で春珍は、
「修行がソレナリに進めば男を求め、結婚する事も許可します。しかし同性愛に進んだ場合は当尼僧院を破門とし、再び、この門をクグルことを許しません。」
と厳しく戒めた。
「サイバーモーメントの黒沢です。え?ナニナニ、そうですか。いえ珍しいので、はい。はい。お任せください。作れますよ。それでは当社へ一度、お越しくださいね。」
サイバーモーメント株式会社・代表取締役社長・黒沢金雄は、おもむろに電話を切った。
その日の午後に黒沢が電話対応していた人物が現れた。和服に頭は頭巾をかぶり、お茶の先生みたいな雰囲気を持つ女性でサイバーモーメント株式会社の受付で、
「社長の黒沢さんに、お会いしたいのです。」
と話した。
「お待ちください。お名前を、よろしいですか。」
「中千家(なか・せんけ)と申します。」
「社長、中千家様が、お見えになっています。・・あ、はい。」
受付女性は社内電話機を切ると、
「あちらのエレベーターで最上階の社長室へ、お上りください。」
高速エレベーターだった。扉が開くと黒沢が立ち上がり、
「中千家様。お待ちしておりました。」
と揉み手をして出迎えた。
応接室では秘書の美月美姫が、冷たい抹茶を出した。
黒沢は、
「さあ、どうぞ。お茶の先生の、お口に合うかどうか分かりませんが。」
と笑顔で勧める。中千家は頭巾をかぶったまま、
「それでは頂きます。」
と答えて、お茶の作法らしい手つきで抹茶を飲むと、
「おいしいですわ。これ、高級抹茶です。」
黒沢は満足げに、
「中千家先生の為に御用意させて、頂きました。入手に少し苦労しましたけど、おほめ頂き、光栄です。」
「早速ですけれど、わたしの弟子に未亡人の方が、おりまして・・・。という事は電話で、お話しましたね?」
「はい。その方が性的な不満を抱えていて男性器の付いた男子ロボットを制作してほしい、という事でしたね。」
「はい、さようで、ございます。お茶の新名門、中千家としましても弟子の希望を叶えたく存じております。」
「ぜひとも叶えられるよう頑張らせて頂きます。男子ロボットの外観についての御希望など、ありますでしょうか?」
中千家婦人は頭巾を右手で撫でると、
「仏像のようなものを希望しています。」
黒沢は少しビックリして、
「仏像!?で御座いますか?」
「ええ色んな仏像が御座いますけど日本や中国、タイにあるような仏像ではなくてチベットにあるような仏像が希望です。その仏像は女人と座ったまま結合している仏像など沢山あります。」
黒沢は得心した顔で、
「いや、これは初耳でした。なにせ仏像なんて見る趣味もなく、女性と無縁な感じの仏像の外観を持つロボット制作なんてと思ってしまいましたからね。チベットの仏像・・・で御座いますね?」
中千家は静かな微笑みと共に、
「はい。チベットの仏像、しかも女体と結合する仏を御覧ください。それから男子ロボットの制作を、お願いします。」
それで中千家は帰って行った。
黒沢は社長室に戻ると大型パソコンでチベットの仏像を検索して調べる。
「なななな、なんと、こういう仏像もあるんだな。初めて見たな、美月、ちょっと、おいで。」
近くにいた秘書の美月美姫を呼ぶ黒沢に、
「はーい。なんでしょう?」
と氷の上を滑るように移動してきた美月に、
「この仏像を見たまえ。」
「きゃっ、交合する仏様・・・。」
「そうなんだよ。チベットの仏像らしい。」
「チベットって、とても変わってますね。」
「変わっているらしい。こういう仏像みたいな男子ロボットを作ってほしいんだとさ。」
「あの中千家さんが、ですか?」
「そうなんだ。作れると思うね。仏像ロボットを。」
その日の夜、黒沢は千手観音菩薩の夢を見た。しかも、その周りには千人の裸の美女がいるのだ。
文字通り、千本の手を持つ観音菩薩は、それぞれの美女の乳房を揉んでいく。
その一本、一本の手が伸縮自在に伸びて、遠くで待機している女の全裸の乳房にも届くのだ。
そして、その手は全裸美女の左右の乳房を位置を変えて揉み愛撫する。
その場所は極楽らしく、広大な温泉地帯らしい。ともかく地球ではないようだ。美女たちは大地に寝そべり、ある者たちは温泉に入った。千手観音菩薩の千本の手は乳房から、彼女たちの股間の秘部へと移っていく。
乳房を揉まれるより感じる部分を千本の手が千のマンコを触り、愛撫し始める。
「ああっ、ははっ。」
「ああーん、いい。」
「あっ、あっ、ああー。」
まさに極楽とは、その場所ではないか。
黒沢は夢だと知りながら見ていて自分も千手観音菩薩になりたいと思った。
目が覚めた当日から黒沢は仏像型男子ロボットの制作に取り掛かる。優秀な技術者数人を指揮した黒沢は、数日でロボットを完成させた。こぶしを握った右手を上げて黒沢は、
「完成したぞー。人工知能も組み込んでいる。さあ、納品だ。」
中千家に完成した旨をメールで伝えると、黒沢は発送したのだった。